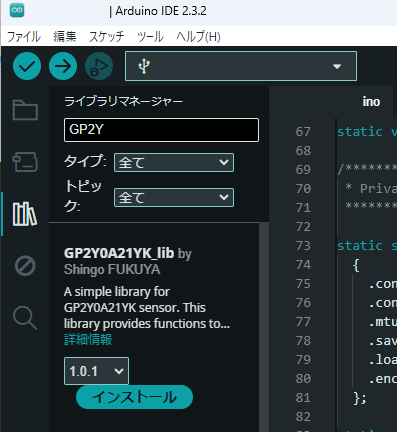2025/12/19(金)SQLite integration
Kojima Toshiyasu版(原作?) SQLite integration
で動作するが、Wordpressを6.5以降にするとDBエラーで全く動かせなくなるので、よくわからないのでずっと放置していた。
それで、この度見つけたのが上述のものを基にした改良版の
wp-sqlite-db
だ。結果これのおかげで最新版のWordpressまで更新が可能となった。
というのもの、一旦このバージョンのSQLite integrationのdb.phpで更新して、その状態からWordpressを6.5以降にアップデート。
こうして一旦経由することでDBエラーがなく6.4と6.5のDB更新を乗り越えることで旧来のSQLiteDBたる.ht.sqliteが引っ越しできた。
そして、次に
SQLiteでWordPressを動かす(その1)
を参考にして、
SQLite database integration のセットアップ方法
も読みつつ、プラグインを手動でpluginsディレクトリにアップロードしインストールしてdb.phpをwp-contentにコピー(上書き)して最新の本家SQLite Database Integrationに移行させた。
これで、ずっと古いままだったWordpressを最新へと更新移行することができた。